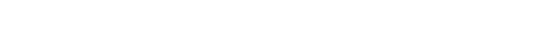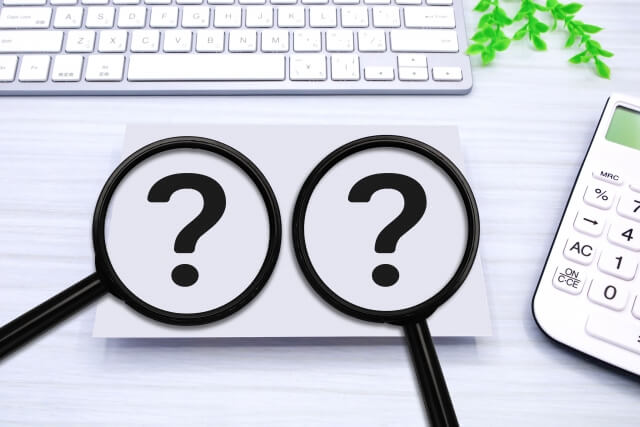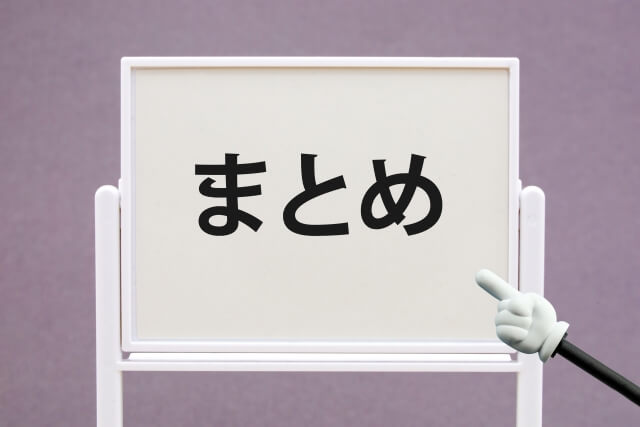―“究極のエコカー”がいよいよ始動―
地球温暖化対策やカーボンニュートラルの実現が叫ばれるなか、輸送の現場にとって避けて通れないのが「大型トラックの脱炭素化」です。ディーゼルエンジンが主流の現在、環境規制は年々厳しくなり、業界全体が新しい動力源を模索しています。その中で注目を集めているのが水素を燃料とする燃料電池トラック。走行中に排出するのは水だけという、“究極のエコカー”です。
目次
【ステアリンク】中古トラックの価格・ラインナップはこちら
-
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 398万円税込 4,378,000円
398万円税込 4,378,000円 - もっと見る
国内初の燃料電池大型トラックが登場
2025年10月、トヨタ自動車と日野自動車が共同開発した大型燃料電池トラックが国内で初めて発売されます。ベース車は日野の大型トラック「プロフィア」。ここにトヨタが「MIRAI」で培ってきた燃料電池システムを改良して搭載し、耐久性や積載性能を確保しました。
これまで実証試験では大手物流企業の協力のもと累計43万km以上の走行テストをクリア。市販化に十分な信頼性が確認されています。
水素の優位性とは?
電気自動車(EV)が注目される一方で、大型トラックに関しては燃料電池が有利とされます。理由は大きく2つ。
1. 長い航続距離
水素は重量当たりのエネルギー密度が高く、満充填で650km以上の走行が可能。長距離輸送に強みがあります。
2. 短い補給時間
水素充填は15~30分ほどで完了。EVの充電に比べて大幅に短く、稼働効率を維持できます。
積載量を犠牲にせず、長距離輸送に対応できる点が物流事業者にとって大きなメリットです。
なぜ今、燃料電池なのか?
乗用車分野では普及が進まなかった燃料電池車ですが、大型商用車では条件が違います。配送の拠点に水素ステーションを整備すればインフラの課題をクリアしやすく、事業者単位で導入を進めやすいのです。
また、企業にとって「環境配慮型物流」への転換は避けられません。荷主企業や消費者からの脱炭素要請に応えるためにも、水素トラックは新しい選択肢として注目されます。
業界再編と水素シフト
日野自動車は2026年に三菱ふそうと経営統合を予定しています。統合後はドイツのダイムラートラックとも技術連携を深め、液化水素を用いた次世代トラックや自動運転との融合が加速する見込みです。
一方でホンダもいすゞと提携し、2027年には燃料電池大型トラックを投入予定。ボルボとの連携も含め、世界的なトラック業界は「水素連合」として動き出しています。日本発の技術が国際競争の中でどのようなポジションを築くのか、今後の展開に期待が集まります。
物流の未来はどう変わるのか?
燃料電池トラックの普及が進めば、都市部での排気ガスや騒音問題は大幅に改善されます。加えて、CO₂削減目標の達成に向けて物流業界が大きな一歩を踏み出すことになります。さらに水素の需要拡大は、再生可能エネルギーでの製造(グリーン水素)の普及を後押しし、真の意味でのカーボンニュートラル社会へとつながっていくでしょう。
まとめ
燃料電池トラックはまだ始まりに過ぎません。しかし、大型車両ならではの特性を生かし、これまで課題だった「長距離・大量輸送と環境負荷の両立」を実現する可能性があります。
いま物流業界に求められているのは、未来を先取りする挑戦です。水素トラック導入は、企業ブランドの強化にも直結します。
【ステアリンク】中古トラックの価格・ラインナップはこちら
-
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 お問い合わせ
お問い合わせ -
 398万円税込 4,378,000円
398万円税込 4,378,000円 - もっと見る